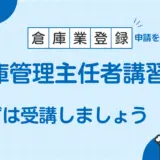倉庫業は、国の登録を受けて行う事業であるため、事業者には一定の義務が課されています。この記事では、倉庫業者が負うべき主な義務と、その義務を怠った場合に下される「事業改善命令」について、分かりやすく解説します。
以下の順番に解説していきます。
- 倉庫業者の義務
- 事業改善命令の法的根拠
- 事業改善命令の対象
- 事業改善命令の具体的な手続き
目次
倉庫業者の義務とは
倉庫業者の義務
倉庫業者に課される義務には主に以下の6つがあります。
- 倉庫寄託約款等の掲示 営業所には、消費者から収受する保管料、倉庫の種類、冷蔵倉庫の場合の保管温度などは、利用者に見やすいように掲示しなければなりません。
- 差別的取扱の禁止 特定の利用者に対して不当な差別的取扱をしてはなりません。
- 倉庫の施設及び設備の維持 施設設備基準に適合するように維持しなければなりません。
- 火災保険に付する義務 倉荷証券を発行する場合には、受寄物を火災保険に付さなければなりません。
- 名義利用等の禁止 名義を他人に倉庫業のため利用させてはなりません。また、倉庫業を他人に経営させてはなりません。
- 名称の使用制限 認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはなりません。
④は発券倉庫業者のみ、⑥はトランクルーム業者のみが対象となります。
営業開始前に必要な手続
また前述の義務以外にも、登録完了から営業開始までに行う必要がある手続きもあります。
- 登録免許税の納付納付書に基づき9万円(新規登録の場合)納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付し提出して下さい。
- 料金の届出(倉庫業法施行規則第24条第1項)保管料、荷役料等の料金を設定又は変更した場合。(実施後30日以内届出)
毎期必要な手続
また営業開始後も毎期ごとに報告書の提出が必要となります。
- 期末倉庫使用状況報告書の報告(倉庫業法施行規則第24条第5項)(当該四半期経過後30日以内に提出)
- 受寄物入出庫高及び保管残高報告書の報告(倉庫業法施行規則第24条第5項)(当該四半期経過後30日以内に提出)
報告書の書き方について詳しくは以下の記事をご覧ください。
 期末倉庫使用状況報告書を電子報告する方法を徹底解説
期末倉庫使用状況報告書を電子報告する方法を徹底解説 そのつど必要な手続
倉庫の設備に変更が生じたり、会社や営業所の住所が変更されたりなど、登録情報の変更がなされた場合は届出が必要となります。是非、以下の記事をご覧ください。
 倉庫業の変更登録を解説:申請が必要な変更と手続きについて
倉庫業の変更登録を解説:申請が必要な変更と手続きについて  倉庫業の軽微変更を解説:届出が必要な変更と手続きについて
倉庫業の軽微変更を解説:届出が必要な変更と手続きについて  倉庫業のその他の変更を解説:申請・届出が必要な変更について
倉庫業のその他の変更を解説:申請・届出が必要な変更について 事業改善命令の法的根拠とは
ここまで倉庫業者としての義務について説明してきましたが、これらの義務に違反しているからといってすべてに事業改善命令が発動されるわけではありません。ここからは事業改善命令についてまずは法的根拠から説明していきたいと思います。
該当条文
まずは事業改善命令の根拠となる倉庫業法の条文について解説します。条文自体は読みにくく、少々分かりにくいので、あとで要約をします。
第15条(事業改善命令)
国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、第8条第2項及び第12条第2項に規定するもののほか、料金の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
少々曖昧ですが『倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実』がある場合、事業改善命令を出せると規定されています。
第8条第2項
『倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実』以外にも以下の事由でも事業改善命令が出せます。
国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。
倉庫寄託約款が利用者の不利益になる場合は、それを改善するために事業改善命令が出せます。
第12条第2項
もう一つ事業改善命令が出せる事由があります。
国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していないと認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。
倉庫の施設・設備が基準に適合していない場合は、事業改善命令が出せます。
第6条第1項第4号
倉庫の施設・設備の基準とは?とのことですが、それは国土交通省令で定められています。
四 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
国土交通省令で定める倉庫の施設・設備の基準については、以下の記事シリーズにて詳しく解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください
 倉庫業審査基準シリーズ目次
倉庫業審査基準シリーズ目次 要約すると
ここまで条文を列挙してきましたが、分かりやすいように以下に要約できます。
- 倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実がある場合
- 倉庫寄託約款が利用者の不利益になる場合
- 倉庫の施設・設備が基準に適合していない場合
2と3については判断できますが、1の「倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実」は少々曖昧です。つぎの章ではこの「倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実」について詳しく解説します。
具体的な基準
さて前項の「倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実」については、倉庫業法では大雑把にしか規定されていません。倉庫業法施行規則等運用方針により詳しく規定されています。
~倉庫業法施行規則等運用方針〔13〕事業改善命令(法第 15 条)より~
1 趣旨
改正前の倉庫業法においては、国土交通大臣は、倉庫業者からの報告や立入検査により、倉庫業の運営上不適切な事実を把握し、これが倉庫の利用者の利便その他の公共の利益を阻害している事実があると認める場合であっても、行政指導を行うにとどまり、法的な措置を講じることができないこととなっていた。このため、事前規制型の行政から事後チェック型の行政への転換を図るため、このような場合に、国土交通大臣が倉庫業者に対し、料金の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる制度を創設したものである。
以前は、法的な措置を講じることができなかったため事業改善命令が創設されたことが説明されています。
2 事業改善命令の発動基準
具体的な事業改善命令の対象について説明されています。2-1では運営全般について、2-2では料金について示しています。
2-1事業改善命令の発動対象は、倉庫業の運営全般にわたるものであり、この発動基準を一律に示すことは困難であり、個別の事情に応じて判断することが必要であるが、例えば、以下のような事例がこれに該当すると考えられる。
イ 保管貨物の管理が継続的に不良なため、少なからぬ荷主に不測の損害を与えている場合。
ロ 冷蔵倉庫の冷却装置の整備不良により冷媒のアンモニアが漏出する等、倉庫周辺に危害が生じている場合。
イとロで具体例を提示しています。不完全な管理により保管貨物が汚損・破損している場合や、帳簿・書類管理の不備のより紛失をして荷主に損害を与えてる場合など、想定される事態は多岐にわたるといえるでしょう。
一方で、料金についても荷主とのトラブルが想定されるため規定されています。
2-2 なお、料金に関する事業改善命令の発動基準をあえて示せば以下のとおりである
イ 倉庫業者が次に掲げる料金を定めた場合であって、これにより倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。
(1) 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、荷主が当該事業を利用することを著しく困難にするおそれがあるもの
(2) 特定の荷主に対し、不当な差別的取扱をするもの
(3) 他の倉庫業者との間に、不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるもの
(4) 荷主にとって容易に理解することが困難であり、荷主に不測の損害を与えるおそれがあるもの(特に、トランクルームについて)
ロ イ(3)については、具体的には、労働コストを含む変動費(保管又は荷役の業務に応じ変動する費用のことであり、原則として人件費、動力費、材料費、下請費用が含まれる。)をもまかなえない市場略奪的な料金等公正な競争を阻害するおそれがあるものが該当するところであり、個別の事例ごとに当該料金に係る地域の市場動向、設定意図、継続性、他の事業に与える影響等を勘案し、総合的に判断すること。
ハ 平成7年運輸省総務審議官通達(倉庫料金届出において原価計算書等の添付を省略できる場合の公示について)のIに掲げる料金の範囲内で個々の料金設定が行われる場合については、当分の間、原則としてイ(1)又は(3)に該当しないものと推定される。
2-2は荷主の金銭的な損害について規定しています。料金について「イ どのような料金が問題となるのか」「ロ 判断の基準は何か」「ハ 例外はあるか」を示しています。
要約すると
事業改善命令の対象となる違反は、倉庫業者としての義務を違反した場合に限らず、運営全般に及びます。また不誠実な料金設定においてもその対象となることがあります。
どのような手続が行われるか
さて、ご覧いただいたように事業改善命令については対象となる項目が幅広く規定されていると言えるでしょう。社会通念上、国の登録を受ける事業として適格でなければ事業改善命令が発動される可能性があります。つまり最初に倉庫業者としての義務を6つ示しましたが、それ以外にも対象とすべきと判断される可能性があると思われます。
倉庫業法施行規則等運用方針では、どのような手続がなされるかも規定されています。
3 手続等
3-1 事業改善命令は行政手続法上不利益処分に該当するため、この発出に当たっては、聴聞を行う等同法の規定に基づき行うこと。
まずは倉庫業者に対して聞き取り調査等が行われます。
3-2 事業改善命令は、公共の利益を阻害している事実の是正のため必要な限度で、当該是正のため必要な期限を定めて行うこと。
聞き取り調査等の結果、事業改善命令が必要な場合は、必要な期限を定めて是正を行わせます。
3-3 3-2の期限を経過しても是正が行われない場合には、倉庫業法第 21 条に基づく処分等を検討すること
期限を過ぎても是正されない場合は、処分がくだされます。
要約すると
事業改善命令はまずは聞き取り調査があります。その後、事業改善命令の対象となることが分かると発動。その後に期限中に是正されていないことが分かれば罰則という流れになります。つまり事業改善命令それ自体は、罰則ではなく、あくまでも是正するための猶予期間といえると思われます。
事業改善命令に違反した場合の罰則
事業改善命令が発動され是正のための期限を過ぎても、改善ができなかった場合についても説明いたします。
5 罰則等との関係
罰則等との関係国土交通大臣の発出した事業改善命令に違反した者は、50 万円以下の罰金に処せられることとなる(倉庫業法第 29 条)とともに、営業停止又は登録取消しの対象となる(同法第 21 条第1項)
50 万円以下の罰金だけでなく、営業停止または登録取消しの処分がくだされることが記されています。
その他の罰則については以下の記事をご覧ください。.
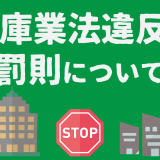 倉庫業法違反の罰則について
倉庫業法違反の罰則について